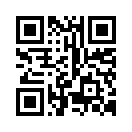2008年04月19日
くるわ

今頃は大阪教室にいる時間です。
というわけでこれは予約投稿になります。
『くすりの社会史』(近代文芸社)という本をたまたま読んでいたところ、そこに遊女の話が出てきました。
沖縄の歌には遊郭絡みの歌が多いのでちょっと興味を惹かれました。
吉原の遊女抱え入れ帳というのによれば、早いもので9歳で連れてこられ、15でお店にデビューし27くらいでほとんどが引退(?)している。
吉屋チルーなんかもわずか8歳ほどで売られていくわけですけど、いきなりお店に出されるわけではなくて見習い期間があって一定年齢になってからお店に出されるようになるのですね。
そんな小さな子がとずっと勘違いしていました。知らなかった。ま、そりゃそうでしょうね。
テレビの時代劇にはこういうの出てこない(大体ほとんど見てもいないけど)のは、なにかあるんでしょうかね。
お店に出て1年もしないうちに何らかの病気に罹り、亡くなっても無縁仏として葬られる。
本にはそのようなことが書いてあり、なんだか悲しくなってしまいました。
時代劇の遊女はかなりの年増だったりするけど実際にはそんなのはありえなくて、半分子供みたいな子らだったりしたんだと思いました。
吉屋チルーも19歳ほどで亡くなったそうだから薄幸ですね。
Posted by sansinzamurai at 16:30│Comments(2)
│日記
この記事へのコメント
吉原も、辻も、遊女のお話は、悲しいですね。
良い唄が、唄い継がれるのが、せめてもの供養ですね。
良い唄が、唄い継がれるのが、せめてもの供養ですね。
Posted by れいちぇる at 2008年04月19日 17:49
ほんとそうですね。
やはり唄の意味は調べて唄わないといけないものだと思いました。
土曜のライブで「金細工」が演奏されましたが、これも遊郭の唄だったんですね。陽気な遊び唄と思っていました。
やはり唄の意味は調べて唄わないといけないものだと思いました。
土曜のライブで「金細工」が演奏されましたが、これも遊郭の唄だったんですね。陽気な遊び唄と思っていました。
Posted by sansinzamurai at 2008年04月20日 14:13