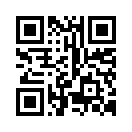2009年01月09日
聞かせる

ヤイリギターでは出来立てのギターにギターの音を聞かせてるそうです。
ギターではないけど、出来立てではないけど三線に三線の音を聞かせてます。
無理やり。
本屋で手にした山下洋輔さんの対談本。
先日ラジオで坂本龍一さんと話されていたのが面白かった。
演奏技術を他人から学ぶのではなく自分で会得したものが後になって何とよばれてるかを知るのはいいものだというようなことを仰られていたような・・・うんうんそうですねと頷きながら聴いてました(現実には頷かないけど)。
開いたページたまたま三味線のことが書いてあり購入してきました。
対談相手は音楽楽研究者の徳丸吉彦さんというかたで、研究のため自ら義太夫三味線を習われた経歴のかた。
たまたま目についたのは、三味線の勘所についての記事。
三味線ではミの音とファ♯の音が狂ってはいけないけど、ファの音はウレイのツボといって個人による揺れがあるのだとか。
同じような楽器をやっていてもいまいちよくわからないことですが、本土の三味線ではファ♯にはサワリがつくために正確な音が得られるということと関係してることのようです。
山下さんは、それについて動いてよい音と悪い音という表現をされていて、わかりやすい表現だと思いました。
あと理論的なことが書かれてますが何のことやら私には・・・(笑)
関係ありませんが、ベトナムの工尺譜のことが載っていて、中国から伝わって宮廷音楽で使われたとあります。
沖縄の古典音楽と似てますね。
どんなものなのか見てみたい感じがします。
『音楽丸秘講座』(新潮社)
Posted by sansinzamurai at 21:16│Comments(2)
│日記
この記事へのコメント
ああ・・・。
なるほど
動いてよい音 悪い音
ですか・・・。
納得です。
ものすごく正確に勘所を抑えて弾く方の音は
確かに安定してるけど 面白み 個性 という点では
少し物足りないかもしれませんね。
何て・・。
実は 私も 勘所をよく外してしまうんで
この記事を読んで 少し安心したのでした(笑)。
なるほど
動いてよい音 悪い音
ですか・・・。
納得です。
ものすごく正確に勘所を抑えて弾く方の音は
確かに安定してるけど 面白み 個性 という点では
少し物足りないかもしれませんね。
何て・・。
実は 私も 勘所をよく外してしまうんで
この記事を読んで 少し安心したのでした(笑)。
Posted by ちゃくら at 2009年01月12日 10:57
ちゃくらさん
先生によっても勘所の位置が違うことがあるみたいですね。
曲によってまんま勘所の位置だと何かかえって変と感じるのもあります。
そのあたり解説してくれる事典みたいのがあると頭の中が整理できていいのになぁと思うのですが・・・・・・(笑)
三下げの曲だと七は気をつけますけど九なんかはけっこういい加減にやってます~。
でも外れつつも楽しんでます(笑)
先生によっても勘所の位置が違うことがあるみたいですね。
曲によってまんま勘所の位置だと何かかえって変と感じるのもあります。
そのあたり解説してくれる事典みたいのがあると頭の中が整理できていいのになぁと思うのですが・・・・・・(笑)
三下げの曲だと七は気をつけますけど九なんかはけっこういい加減にやってます~。
でも外れつつも楽しんでます(笑)
Posted by sansinzamurai at 2009年01月12日 17:00