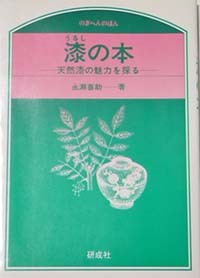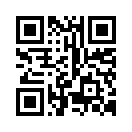2007年03月30日
『沖縄うたの旅』
 音楽評論家、青木誠さんの本。
音楽評論家、青木誠さんの本。古代に始まり16世紀の『オモロソウシ』以降発展してきた沖縄の芸能を豊富な薀蓄とユーモア交えて書かれています。
大和の七五調のリズムは念仏歌の節としてあみだされ、江戸期に七七七五の小唄の形式ができたのだとか(そういえば浄土真宗なんかでは、お経は唄のように唱和され最後になんとかかんとか「なむあみだ」と唱えられていたような気がする・・・今度じっくり聴いてみよう)。
対して沖縄の琉歌は音感の違いで八八八六となったのだとか、このあたりちょっと飛躍してる感じがしないでもないけど、そんなことはともかく、赤犬子伝説や古典曲、組踊りの発祥など沖縄音楽の歴史やミステリイが興味をそそります。
歌舞伎と比べられる組踊りは、江戸にのぼる通訳が元禄期の歌舞伎と能をモデルにチャンプルしたものと知ったり・・・興味のあるかたは本で読んでいただくとして、モーアシビで歌い踊られる曲に自分がまじめに練習している「嘉手久」や「加那よー節」が出てきて(笑)。「アッチャメー小」とか「ナークニー」とかこれからやりたい曲もそのあたりの曲だったとは・・・でも考えてみると自分はイベントに関わることをやっているから結局同じことかと、沖縄のその時代に生まれていたら自分はモーアシビの地謡でもやっていたのかなと想像してしまいました。
1995年の「沖縄うたの旅」の新装改訂版。
2000年8月15日発売。ボーダーインク(沖縄)刊。
Posted by sansinzamurai at 03:23│Comments(2)
│沖縄の本
この記事へのコメント
普段七五調に慣れてる私たちには、沖縄琉歌の
八八八六ってなかなか馴染みにくいんですよね・・。
私は歴史的には、勝連城のアマワリの時代に興味があります。
この頃の歴史本は、かなりよく見かけますよね。
でも、いろんな説があって、なかなか奥深いですね・・・。
私はすぐ妄想するタイプなんで、勝手に超男前のアマワリ像とか作って
楽しんでます(笑)
八八八六ってなかなか馴染みにくいんですよね・・。
私は歴史的には、勝連城のアマワリの時代に興味があります。
この頃の歴史本は、かなりよく見かけますよね。
でも、いろんな説があって、なかなか奥深いですね・・・。
私はすぐ妄想するタイプなんで、勝手に超男前のアマワリ像とか作って
楽しんでます(笑)
Posted by ちゃくら at 2007年03月30日 19:03
>八八八六ってなかなか馴染みにくい
そうですね。
八八八六で考える習慣をつけたらいいのでしょうか^^;
ちゃくらさんは歴史の研究とかたくさんされてそうですね。
私は最近ようやく目覚めつつあるところです。
諸説入り乱れて想像が広がりますね(^^ゞ
そうですね。
八八八六で考える習慣をつけたらいいのでしょうか^^;
ちゃくらさんは歴史の研究とかたくさんされてそうですね。
私は最近ようやく目覚めつつあるところです。
諸説入り乱れて想像が広がりますね(^^ゞ
Posted by sansinzamurai at 2007年03月31日 05:01